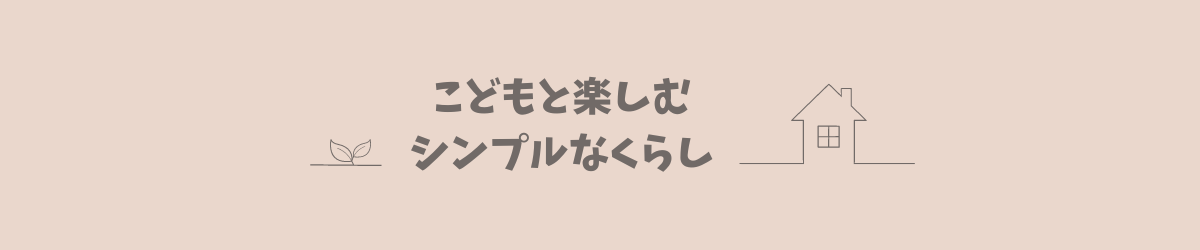わが家は今月から夫婦で時短勤務をしています。
パパも時短勤務ということ?
今月は、10ヶ月になった長男の保育園入園と、わたしの職場復帰の月。
夫はもともとフルタイム勤務でしたが、このタイミングで時短勤務に変更しました。
今日は、わが家が夫婦で時短勤務を選択するに至った理由と、夫婦で時短のメリット・デメリットを解説します!
時短夫婦が効率的に家事をこなすための必須アイテムもご紹介ているので、ぜひ参考にしてみてください!
- 夫婦で時短勤務のスケジュール
- 夫婦で時短勤務のメリット・デメリット
- 時短夫婦の必須アイテム9選
4児のママ、あいです!
- 2男2女のママ
- 整理収納アドバイザー1級のお片付けマニア
- 頑張らずに子育てを楽しむ方法について発信中!
夫婦で時短をはじめたきっかけ

夫婦で時短勤務を始めたとき、わが家の家族構成は、
- 夫
- わたし
- 長女5歳 (A保育園・年長)
- 二女2歳 (A保育園・2歳児クラス)
- 長男0歳 (A保育園分園・0歳児クラス)
の5人家族。
未就学児の子どもが3人いるので、何をするにも大人一人では手が足りません。
長男は授乳中ですし、トイトレ中かつイヤイヤ期後半の二女もまだまだ手がかかります。
さらに長男の保育園は上の子たちと別の場所なので、送迎は2箇所です。
いくらわたしが時短勤務をしたとしても、子ども3人を連れて帰宅したあとどんな状況が待っているのか・・・想像に難くありません。
疲れて帰ってきたら家族5人分の家事と子ども3人分の育児が待っていて、しかもワンオペ・・・
子どものために働いているはずなのに、子どもに当たってしまうかもしれない。
家族の健康が第一なのに、食事づくりが疎かになってしまうかもしれない。
そんな本末転倒な状況は避けたい!
この状況を打破するには、夫にも時短勤務してもらうしかない!
これが、夫婦で時短勤務をはじめたきっかけです。
働く目的ってなんだろう?

みなさんにとって、「働く目的」とはなんですか?
お金を得るため?仕事が好きだから?
子どもが生まれるまでのわたしたち夫婦は、正直言って「お金を得るため」に働いていました。
お金をもらうためなんだから、残業も休日出勤も仕方ないし、仕事が終わらないから帰らないのは当たり前、だと思っていました。
でも、今は違います。
今のわが家の「働く目的」は、「家族の幸せのため」です。
仕事は、自分を含めた家族みんなの幸せのためにするもの。
仕事をすることで自分や家族に負担がかかることはしない。
だから、仕事が終わらないから帰れないのではなく、時間内に終わるように仕事をする。
仕事で会えないのが当たり前ではなく、一緒にいられるような働き方をする。
そして、仕事をしていない時と同じくらい、時間と心に余裕を持って子どもたちに接することができる親でいる。
そんな考えのもと、仕事と家庭に向き合っています。
家族の幸せが1番大切だから。家族の笑顔を守りたいから。
子どもに手がかかる今は、夫婦で時短勤務をする必要があると決断したのです。
働き方が変わるまで

働く目的を見失っていた頃
そんなわが家ですが、仕事のために自分たちの生活を犠牲にしていた時期もありました。
6年前。長女が生まれたころの夫は仕事が忙しく、いつも帰宅は日付が変わる頃。
土日もどちらかは休日出勤していて、休みの日は疲れてぐったりという状態でした。
夫は、長女と触れ合う時間がほとんどなく、パパに抱っこされると泣くし、家事はほぼノータッチ。
夫婦で会話する時間も少なく、顔を合わせるのは朝の1時間程度。夫婦間のすれ違いや衝突も増えていきました。
夫が残業をすればするほど給料は増えたけれど、家族の時間は減っていく。
寝て起きて仕事へ行って、帰ってきたら食べて寝て、次の日も同じことの繰り返し。
家族で団らんする時間もなく、ロボットのように働く夫を横目に、わたしははじめての育児に精神的にも追い詰められていきました。
これじゃあいけない。
なんのために働いているのか、なんのために生きているのかさえわからない。
長女が1歳になる頃、やっと自分たちの毎日が「働く目的」を見失っていることに気づき、「変わろう」と決意します。
大切な家族のため。愛する子どものため。
本を読んで勉強し、仕事に向き合う根本的な意識から働き方を変えていきました。
働き方を変える!
まずはじめにやったことは、仕事のために睡眠を削るのではなく、仕事の集中力を上げるために7時間の睡眠を取るようにしました。
いい加減になっていたわたしの時短勤務も、帰ると決めた時間で退勤するようにしました。
家事の段取りも変えました。
ロボット掃除機や食洗機をフル活用し、ネットスーパーなどのサービスも遠慮なく活用するようにしました。
そうやって「仕事時間」と「家事時間」を可能な限り効率化することで、大切な「家族時間」が少しでも増えるようにしていきました。
すると、子どもと過ごす時間が少しずつ増えていき、心の余裕もでてくるようになりました。
平日の夜でも、家族とゆっくり過ごせる。休日は、家族で出かけられる。
明らかに生活への満足度が高まっていく実感がありました。
数ヶ月すると、夫の残業の状況は少しずつ改善していき、長女が3歳になる頃には、月100時間超の残業していた夫が、ほぼ残業しない働き方を手に入れました。
そんな頃に誕生した二女。
夫は、長女のときとは比べものにならないくらい二女の育児に積極的に参加でき、二女はパパが抱っこしても泣かない、授乳以外はパパでも大丈夫な「パパ大好きっ子」になりました。
その2年後に生まれた長男のときには、夫が初めて半年間の育児休業を取得。
わたしが復職した現在は、夫婦で時短勤務をしているというわけです。
夫婦で時短勤務のスケジュール

夫婦で時短勤務だと、どんなスケジュールになるの?
わが家の一例をご紹介します!
朝のスケジュール
▼出勤前
〜6:00 自由時間
6:00〜 家事開始 (食洗機片付け、朝食、大人2人分のお弁当づくり、身支度)
7:00〜 子どもたち起床 、(なかなかすぐには動き出せないので時間がかかる)、
トイレ・オムツ交換
7:20〜 みんなで朝食・長男の離乳食
7:50〜 朝食片付け、歯磨き、着替え
8:10〜 長男授乳、長女二女の髪の毛を結ぶ、連絡帳アプリ記入、ゴミ出し
8:30〜 自宅出発 (全員で出発、わたしと夫で二手に分かれて送迎)
帰宅後のスケジュール
▼退勤後
〜16:30 長男お迎え(ママ)
〜16:40 長女、二女お迎え(パパ)
16:55 全員で帰宅
17:00〜 長男授乳、子どもたちと遊ぶ
17:20〜 夕食準備(ママ)、洗濯物片付け・子どもの相手(パパ)
18:00〜 夕食
18:50〜 夕食片付け、子どもたち歯磨き
19:20〜 入浴 (①パパ→②長女・二女→③長男・わたしの順に全員で入浴)
20:20〜 ドライヤー、水分補給、お風呂掃除(パパ)、長男授乳
20:50〜 絵本タイム、就寝
こうしてみると時間的にかなり余裕がありそうにみえますね。
でも実際は、子ども3人の気分や都合に合わせながらなので、かなりドタバタしています。
もし子ども3人を育てながら時短勤務をしていなかったら・・・と思うとゾッとするほど恐ろしいです。
時短勤務のメリットとデメリット

家族の時間も増えて心の余裕も持てて、夫婦で時短勤務はいいコトだらけ?
もちろん、夫婦で時短勤務はいいことばかりではありません。
次は、わたしが考える夫婦で時短勤務のデメリットを解説します。
夫婦で時短・デメリット
- 勤務時間が短い分、給料がカットされる
- 勤務時間が短い分、関われる仕事に制限がかかる
- 職場に迷惑をかけていると感じる
- 時間的制限があることに加え、子どもの発熱など、突発的な対応も求められる
- 子どもの多少の体調不良なら、登園させざるを得ないこともある
小さな子どもを預けて働くことは、子どもの体調不良時に急なお休みや早退をしなければならない確率が高いです。
時短勤務をしていると、勤務時間が短いことに加えて、そのような突発的な対応もしなければならないのです。
勤務時間が短い上に、お休みや早退ばかり・・・「職場に迷惑をかけている」という心苦しさが、いつもわたしの心に影を落とします。
だから、少しくらいの風邪であれば、子どもを登園させざるを得ない時もある。
仕事が予定どおりに進まないのは当たり前。
予定どおりに進まない前提で仕事を組み立ててはいるけれど、今日は呼び出しの電話が鳴らないでほしい・・・
祈るような気持ちで、肌身離さず携帯電話を持っています。
仕事で貢献したい気持ちと時間の制約による焦れる気持ち、子どもに無理をさせてしまうことなどへの葛藤に、母になって6年たった今でも苦しんでいます。
夫婦で時短・メリット
一方で、夫婦で時短勤務をするとメリットもたくさんあります。
- 家族で過ごす時間が増える
- 時間的・精神的余裕をもって、子どもと接することができる
- 少しずつではあるが、3人の子どもひとりひとりと向き合う時間が持てる
- 夫婦で向き合う時間が持てる
- 食事作りや掃除など、自分の納得がいくレベルの家事ができる
- 日々の暮らしへの満足感が高まる
数えてみるとメリットのほうが多かった!
夫婦で時短勤務をすることで、家族で過ごす時間は格段に増えました。
1日8時間のフルタイム勤務をしているときと比べたら、時短勤務にしている2時間分は家族と過ごす時間が増えています。
年間240日勤務していると仮定すると、480時間も「家族時間」が増えることになります。
たった2時間?
でも、時間的な余裕があるからこそ、子どもがぐずったり、甘えたり、わがままを言ったりしても、精神的な余裕をもって子どもと接することができています。
長女の話を聞いてあげ、二女の甘えに付き合い、長男にはゆったりと授乳をしてあげらる。もちろん、夫婦の会話の時間も以前よりぐんと増えました。
毎日の食事やお弁当作り、掃除や洗濯といった家事も。
ここまではちゃんとやりたい、と思う自分の価値観に基づいて、我慢せず、納得のいく暮らしができています。
過ぎた時間は取り戻せないからこそ、納得のできる今を過ごし、暮らしていたい。
夫婦で時短勤務をすることで、毎日の暮らしに対する満足感が高まり、その結果、仕事への意欲も増すようになりました。
時短夫婦の必須アイテム9選

いくら夫婦で時短勤務でも、子ども3人もいたら忙しそう・・・
そのとおり。でも家電やサービスに頼ってうまくやりくりできています!
ここからは、夫婦で時短勤務をしているわたしたちが頼りにしている、効率的に家事をこなすための必須アイテムをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください!
ドラム式洗濯乾燥機

時短夫婦のみならず、忙しい共働き世帯や子育て世帯には絶対活用してほしいアイテムNo.1!
初期投資額は大きいですが、1日20〜30分くらいの時間を生み出せます。
電気代が心配でしたが、夜間電力を使って深夜に洗濯・乾燥しているので、数百円しか変化なし。
天気を気にせず洗濯できるのと、翌朝にはすっかり乾いているので、衣類のストックも最小限で良くなりました。
おかげで洋服代が節約でき、収納スペースの削減にもなっています!
どうしても乾燥できないものや、乾燥するとしわくちゃになって困るものは、分けて洗っています。
使っているのはパナソニックの泡洗浄シリーズ!
心配していた汚れ落ちは、縦型と比べて申し分ないです。
洗剤の自動投入機能付きを選べば、さらに時短になりますよ!
夫のワイシャツも乾燥していますが、ほとんどシワなく仕上がります!(ユニクロのノンアイロンシリーズです)
食器洗い乾燥機

こちらも初期投資額は大きいですが、洗って拭き上げてといった作業が無くなるので、1日20分以上の時間を生み出しています。
予洗いはある程度必要ですが、洗いから乾燥までボタン一つでお任せ。
高温で乾燥するので、衛生状態が気になる生肉を切ったキッチンバサミなどもキレイに洗ってもらっています。
手洗いよりもピカピカです。
戸建て購入時に導入したので電気代の変化はわかりませんが、夜間電力で深夜に稼働しているので全く気になりません。
工事不要の食洗機もありますよ!
ロボット掃除機

ロボット掃除機も子育て世帯の強い味方。
寝ている間、外出している間にお掃除してくれるので、時間を節約できるんです。
わが家には2台あって、薄型のキーボルを1階用に、ダイソンを2階用にしています。
ロボット掃除機って高額なイメージ・・・
いまはお手頃価格で優秀なロボット掃除機がありますよ!
キーボルは2万円くらいで買えるので、有名メーカーのロボット掃除機に比べてかなりお手頃!なのにしっかり働いてくれます。
薄型なので、高さ10センチ以下のソファーや家具の下もスイスイ。いつ見てもホコリがたまっていないのが気持ちいいです。
水拭き機能は不要なので、水拭きなしのモデルなら1万円ちょっとで購入できそうです!
知ってましたか?室内のホコリは数時間かけて床に落ちていきます。
しっかりお掃除したいなら、人がいなくなって数時間たってから(=浮遊しているホコリが床に落ちきってから)掃除機を稼働させるのが正解なんですよ!
だから、外出後または就寝後、数時間経ってから稼働するようにタイマーをかけておけば、さらに効率的にお掃除ができます!
浄水器

必須アイテムの中では一番最近導入したものです。
なんのために導入したの?
お茶を作る時間を短縮するためです!
浄水器設置前は普通の水道水を沸かしてお茶を作っていました。でも、このお茶を作る作業が結構面倒・・・
家族が増えると飲むお茶の量も増えるし、できたてのお茶は熱すぎるので冷ます時間も必要です。
家族5人・・・夏になったら一日何回お茶を沸かせばよいのやら・・・と頭を抱えていました。
そこで!7年使った水栓を浄水器付きのものにリフォームしました!

選んだのはリクシルのナビッシュ。
浄水器ついでにハンズフリーのタッチレス水栓にしたのですが、これが大正解!
水出しでお茶を作れるようになった分、お茶づくりの時間がほぼゼロに。
水道水を沸かして作ったお茶よりも明らかにおいしいし、ハンズフリーのおかげで下ごしらえや洗い物が以前より断然早くなりました。
成分のことを追求したらミネラルウォーターには敵わないと思うけれど、それでも浄水器のおかげで時短とおいしさを手に入れました!
食材の宅配

食材の買い出しって、子ども連れだと時間がかかるし荷物もあるから正直大変ですよね。
仕事をしていると平日はなかなか買い物に行けないし、休日はゆっくり休みたい・・・
週末は翌週のメニューを考えながらお買い物をするのが定番です。
わたしもそうでした!でも、いつも買うものは自動で届いたらラクなのに・・・なんて思いませんか?
それならパルシステム!
「パルくる便」といって、定期的に頼みたいものを登録しておけば注文不要で届けてくれるサービスが便利です。
わが家では、たまごや納豆、お豆腐、お肉、牛乳といった固定メンバーはパルくる便頼み。
仕事で不在にしていても玄関先に置き配してくれるので受け取りの心配は不要です。
また、パルシステムは乳児向けの商品も充実しているので、離乳食期の赤ちゃんを育てるママにはその間だけでもぜひ使ってもらいたいです。
(わたしは、1人目が生まれてすぐにパルシステムを始めました!)
パルシステムは1都11県が対象エリア(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、福島、山梨、静岡、新潟、長野)なので、エリア内にお住まいのママは一度チェックしてみてください!
それと、少しでも有機野菜を取り入れたいという思いから、月に1回「ビオ・マルシェ」と「食べチョク」も使っています。
ビオ・マルシェは有機野菜のみの野菜セットが魅力。食べチョクは、全国の農家さんとマッチングできるので、愛情たっぷりに育てられた旬のお野菜を楽しめます。
ほかにも、離乳食期のお悩みについてはこちらの記事が人気です。

ネットスーパー

生協にもお世話になりますが、ネットスーパーも使っています!
どうしても週の途中で必要なものが出た場合や、ちょっとだけ買い足したいときに便利です。
最短で当日に届けてくれるので、出勤前や通勤中のスキマ時間に注文・・・帰宅する頃に合わせて配達してもらえば買い物時間ゼロ。本当に助かります!
わたしがよく使うのはイオンとイトーヨーカドーのネットスーパー。
イオンは品数が豊富。
食品だと、イオンのPBブランドであるトップバリュはもちろん、グリーンアイオーガニックやグリーンアイナチュラルのシリーズが大好きでよく利用しています。
また食材以外にも日用品や衣類、学用品まで揃うので、ついでにポチ。
配達料は少しお高めですが、購入金額に応じて配送料が無料になるサービスもあります。
イトーヨーカドーは子育て世帯には優しい配達料の優遇措置があって、ちょこっと買いのときに便利です。
配達時間も細かく分かれていて帰宅時間に合わせて配達してもらいやすいのも魅力的。
ネットスーパー専用バスケットで配達してくれるので、ゴミが出ないのも◎です。
注文用のアプリも充実していて、操作性もとても良いですよ。
電動自転車

ずっと車1台だけだったわが家ですが、3人目の保育園入園が決まってから電動自転車を購入しました!
購入の理由は、3人目の送迎場所が離れてしまったから!
同じ保育園なのですが、定員の都合でお姉ちゃんたちとは離れた分園になってしまったんです・・・
春には一番上の長女の小学校入学も控えていて学童も含めるとお迎えが3箇所になることがわかっていたので、それらも見据えて購入を決めました。
購入の際はパナソニック、ヤマハ、ブリヂストンの3社で検討。結果、パナソニックのギュットクルームに決めました。
決め手は、前側のチャイルドシートの乗せやすさ!足元が他と違ってガバッと開くんです。
ギュットクルームのチャイルドシートはコンビ社とコラボしています。車のチャイルドシートがコンビの方は使いやすいですよ!
電動自転車を購入したお陰で、車と自転車で送迎を分担できるようになりました。
また、送迎以外にもちょっとしたお買い物のときや、歩いて行くにはちょっと遠い公園まで出かけられるように。
車では埋められなかったわたしたち家族の希望が叶うようになってとても満足しています!
宅配ボックス

宅配ボックスは3年くらい前に導入しました。
理由は、2人目の子が生まれてネットショッピングをする機会が増えたのに、授乳中に応対できないのが困ったから。
子どもが小さいとネットショッピングが便利ですが、授乳中にインターフォンが鳴ると出られない・・・
時間指定してまで届けてもらった荷物も受け取ることができないこともあり、申し訳なかったんです。
そこで、思い切って宅配ボックスの設置に踏み切りました。
選んだのはパナソニックのコンボライト(ミドルタイプ)。わたしの感覚として95%の荷物が入る十分な大きさがあります!
宅配ボックスは、家を建てたときには考えもしなかった設備。
後付けですが、宅配ボックスを設置したお陰で配達を気にせず外出できるようになりました。
時間指定をしたり、時間までに帰らなきゃと焦ることもなくなり、ストレスフリーに。
コロナになって「置き配」が当たり前になりましたが、やっぱり鍵付きボックスに入れてもらえると安心です。
本当は配達員さんに直接お礼を言って受け取るのがベストだと思いますが、再配達は悪いので・・・導入してよかったです!
こちらの記事でも解説しています。

重ね煮

必須アイテムの最後は、ママなら絶対知っていてほしい調理法「重ね煮」です。
食材を順番に重ねて煮るだけで、旨味が引き立ち、少ない調味料でもおいしいごはんが作れちゃう調理法です。
「煮る」調理法なので、味付け前に取り出して刻めば離乳食もカンタン。大人と赤ちゃんのごはんを別々に作る必要はありません。
わたしが一番驚いたのは、味付けに使用する調味料の少なさ!しょうゆや塩だけでこんなに美味しくできるんだ・・・と感動したのを覚えています。
重ね煮は、切った順に鍋に入れていけばOKなのでボール不要。油も使わないので洗い物も楽ちんです。
煮ている間は他の作業ができるので家事がはかどるといった具合にいいことづくめ。
「つくりおき」も「下味冷凍」も挫折してしまったたわたしでも(笑)3年以上続けられている「重ね煮」。
「◯◯のタレ」に頼らなくても手作りごはんを続けられているのはとにかく簡単で疲れていてもできる調理法だから。
ぜひ一度試してみてほしいです!
ママにおすすめの「重ね煮」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

今日は、わが家が夫婦で時短勤務を選択するに至った理由と、夫婦で時短のメリット・デメリットを解説しました。
わが家では「働く目的」である「家族の幸せ」を実現するため、夫婦で時短勤務するデメリットを受け入れた上でメリットを享受しています。
ただし、夫婦で時短勤務をするという働き方が実現するのは、この働き方を実現させてくれる職場があってこそのこと。
職場の理解や協力、支援を得ることができているから、夫婦で時短勤務をすることができています。
わたしたち夫婦の「働く目的」に対する意識が変わったことだけでなく、それを受け入れてくれた職場があったからこそできる働き方なのです。
だから、職場への感謝の気持ちもまた、仕事で貢献する力に変えていけています。
だけど現実は、時短勤務をしていたって子どもに無理をさせてしまうこともある。
泣いているわが子の、風邪を引いているわが子の、小さく非力な手を自分から離して保育園に預けなければならない現実もある。
その現実は、母親として心が痛まない日はありません。
時短勤務ができることのありがたさを感じつつも、子どもを預けて働くことの大変さも痛感する毎日です。
仕事をしなければ食べていけないけれど、自分の守りたいもの、守るべきものを守れるのは自分だけ。
家族で一緒に過ごす時間に価値を感じるわたしたち家族にとって、今できる最善策が夫婦で時短勤務をすることでした。
でも、この働き方ができるのはやっぱり職場のおかげ。
だからこそ、職場へ感謝の気持ちと、「今の自分のできる最大限の範囲で貢献していく」という強い決意のもと、これからもわが家らしく歩んでいきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
こどもと楽しむシンプルなくらしをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。