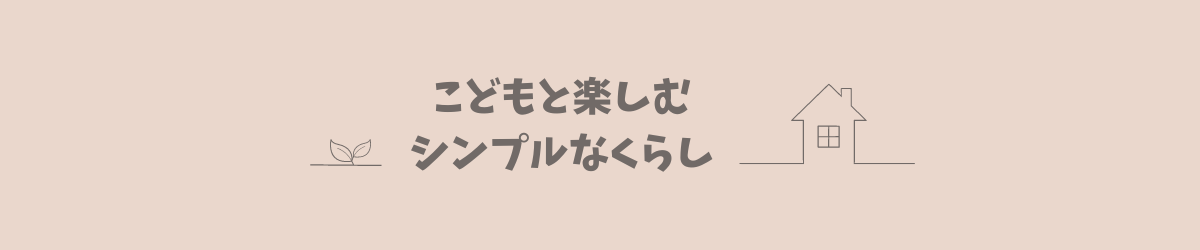図書館で借りてきた絵本の収納方法がうまくいかなくて・・・
それならいい方法がありますよ!
図書館で借りてきた絵本。
置く場所がないとか、読み終えた絵本が散らかって困ると言ったことはありませんか??
絵本を返すつもりで図書館に行ったのに、1冊足りなかったなんてことも・・・
- 借りてきた絵本の収納が定まらない
- 読み終わった絵本が散らかって困る
- 借りてきた絵本を管理するのが大変
実はこれらの悩み、以前のわたしの悩みです。
こんなふうに、図書館の絵本は借りたり返したりの管理が必要。おうちの絵本とは区別しなければならず大変!ですよね。
わたしもはじめは絵本の管理が大変だと思っていましたが、ある収納方法に変えてから図書館を使い倒せるようになりました!
今日は、整理収納アドバイザー1級でもあるわたしが、無印良品の商品を使って3年以上続けている頑張らない図書館絵本の収納法をご紹介します!
図書館絵本の収納を攻略すれば、子どもにとって本がもっと身近な存在になりますよ!
- 図書館絵本をスッキリ収納する方法
- 図書館絵本の収納アイディア
4児のママ、あいです!
- 2男2女のママ
- 整理収納アドバイザー1級のお片付けマニア
- 頑張らずに子育てを楽しむ方法について発信中!
本好きな子に育てるなら図書館
図書館は自分の本棚!

わが家が図書館に頻繁に行くようになったのは、長女が2歳になったころ。
それまでの長女は、授乳後にそのまま就寝していたので、寝る前に本を読む習慣がなかったんです。
2人目を希望していたので、2歳を目前にして断乳に踏み切ったのですが、授乳の代わりに始めたのが絵本タイム。
最初は自宅にあった数冊の絵本からはじめ、飽きてきたころに書店に買いに行く・・・ということを繰り返していました。
でも、絵本もなかなか高価。月に何冊も買ってあげられないため初めて図書館を利用してみようと思ったんです。
毎月何十冊も買えないけれど、図書館なら無料。図書館のおかげでたくさんの絵本を読んであげられています。
図書館だから気軽に試せる

「絵本を読んでから寝る」というルーティンが確立してからは、絵本がないと眠れなくなった長女。
「今日はもう遅いから絵本はなしよ〜」なんていうと、「やだー!」と怒られる始末です。
気になった絵本はなんでも借りてみるスタイル。10冊借り1冊でもお気に入りの絵本が見つかれば良し!と思っています。
どんな絵本がヒットするかもわからないので、いろいろなジャンルの絵本を気軽にお試しできる図書館の存在は本当に頼りになります。
子どもも、新しい本を借りてくるとワクワクしているし、子どもの反応が楽しみで大人も密かにワクワク。
書店だと、「1冊だけよ」と言わなければならないところ、図書館では「10冊OKよ!」と言ってあげられるので、本棚を物色する子どもたちを穏やかな気持で見守れるんです。

未知の世界がつまった絵本は旅をしているようで楽しい。今では、わが家の生活に欠かせないくなった図書館という存在。
図書館に通うには時間も労力もかかるけれど、たくさんの「未知」や「わくわく」がつまった「本」を好きになって、大人になっても自然と本がそばにある生活を送ってもらいたい!
そんな思いで通い続けています。
今は、インターネットで自宅からでも蔵書検索がカンタンにできるので、読みたい本が見つかるとすぐに検索して予約しています。
「図書館絵本」の収納法とは?

わが家では、2週に1回、10冊以上の絵本を借りてきます。かなり重いし収納スペースもとってしまう・・・
でも、読み聞かせが子どもにとっていいことがわかっているので、ついつい借り過ぎてしまうんですよね。
そんなたくさんの絵本、管理するのが大変なのでは・・・?と思いますよね。
でも、これからご紹介する収納方法に変えてから3年以上、頑張らなくても図書館を使い倒せています。
プロが3年続ける頑張らない収納法は?
では、お片付けのプロはどうやって頑張らない収納を実践しているのか。
その答えは、自立するバックに入れて、絵本の収納と移動を兼ねるようにすることです。

図書館の絵本は、借りたり返したりするので移動する機会が多め。
さらには、家の中でもリビングや寝室、子ども部屋など、読みたい場所へ移動させることがありますよね。
お片付けのプロが3年続けている図書館絵本の頑張らない収納法とは、収納も移動もできてしまう「兼ねる収納」にすることなんです!
プロ愛用!図書館絵本の収納グッズ
使っているのは、無印良品の「持ち手付帆布長方形バスケット」。
バスケットというだけあってかなりしっかりしたお作り。
ちゃんと自立するので子どもでも絵本の出し入れがしやすく、何冊入れても倒れない優れものです。
3年以上使い続けていますがまだまだ壊れることなく現役です。
※2023.06.11追記 無印良品で廃盤になった可能性があり入手困難となりました。
ぜひ再販してほしいです。。
代わりに、似たような商品を見つけました!
サイズもほぼ同じ。帆布で作られているので丈夫だと思います!!
持ち手にはハンドルカバーを付けるのがおすすめ。
絵本を何冊も入れて重たくなっても、ハンドルカバーのおかげで感触がソフトになりとっても持ちやすいです。
また、持ち手の汚れ防止にもなっています。
(わたしが使っているハンドルカバーの色はキャメルです。)
こんなフェルト製のファイルボックスも良いですね。
最近、無印良品でもフェルト製のファイルボックスが発売されましたね!
わが家では移動と収納を兼ねる「兼ねる収納」のおかげで、図書館絵本の管理がぐんとしやすくなりました。
なるべくたくさんの絵本に触れさせてあげたい。
散らかるのはイヤだけど、図書館の絵本は借りてきて読んであげたい。
そんなかたは、収納と移動を兼ねる「兼ねる収納」がおすすめです。
収納も移動も兼ねられる頑張らない収納!借りている間も見た目が美しく、移し替える手間もないので貸し借りがラクになります。
図書館絵本の収納実例!昼間は?

図書館で借りてきた絵本は、日中はだいたいソファーのそばに置いてあります。
あさ保育園へ出かける前や保育園から帰ってきたあとなど、子どもたちの好きなタイミングで読まれる絵本たち。
ご飯を作りながら「なんだか静かだな?」と思って見に行くと、絵本をめくっていた、なんていうことがよくあります。

借りてきた絵本の存在が忘れ去られていたり、この本はぜひ読んでもらいたい、という絵本があるときは、こっそりディスプレイして存在をアピールすることも。
子どもは、ディスプレイされた絵本見つけると「なにこれ?」と言いながら自然に手に取り読み始めます。
人気YouTuberのてぃ先生がおすすめしていた方法です。ちょっとしたことですが、子どもはすぐ反応してくれるのでやりがいがありますよ。
図書館に通いだしてから、以前よりぐんと本を手にとる機会が多くなって明らかに本が好きになった子どもたち。
「兼ねる収納」のおかげで一月に20冊以上、年間にすると240冊以上の絵本を読んであげられるようになりました。
もともと自宅にあった絵本も読まれる機会が増えて、親としてはうれしい限りです。
無印良品の帆布バスケットを使った「兼ねる収納」を採用して3年以上。
子どもたちも「図書館で借りてきた絵本はここに入れるもの」と認識していて、読み終わったら帆布バスケットに戻すことが定着しています。
だから、図書館で借りてきた絵本とおうちの絵本と混ぜて片付けてしまうことはなく、「紛失や返し忘れ」もありません。
図書館絵本の収納実例!夜になると?
図書館で借りた絵本は、夜になると寝室に運ばれていきます。(運搬はパパ担当(笑))

寝る前のリアルな寝室を撮影してみました。絵本は朗読担当のパパの枕元に。

ここから、子どもたちがその日の気分で読みたいものを取り出して、絵本タイムが終わったらみんなで就寝。それがわが家の日常です。

バッグの中には、図書館に行くとき必ず必要になる図書館カードも一緒に収納します。

子どもが持ちたがるので、首から下げられるちいさなポーチをハンドメイドしました。

中には4人分の図書カードが入っています。
このように、図書カードも図書館バッグと一緒に収納するのがプロのおすすめ。
図書館バッグと一緒に収納するようになってから、図書館カードの忘れ物がなくなりました!
たくさん借りる場合はバスケットタイプがおすすめ
こんなコンテナもかわいいですね!
プラスチック製のバスケットも、最近はおしゃれなものが多く出ています。
使わない時は畳んで置けるタイプのものなら収納場所にも困りません。
一度に10冊以上の絵本を借りてくる!という絵本大好きなご家庭におすすめです。
スーパーのマイバスケット的な感じです!使わない時は畳んで収納できるものを選んでくださいね。
借りる絵本が少ない場合の収納は?

借りる絵本が少ない場合や、自転車や徒歩で図書館に行く!というママにとっては、大きくてかさばるバスケットでは使いづらいですよね。
また、図書館に行くのは車だけどいつも数冊・・・2〜3冊がちょうどいい・・・というママも多いと思います。
バスケットに入れるほどたくさんは借りないけれど、1冊でもないな・・・という場合は、つぎのような収納がおすすめです。
- 「図書館バッグ」を決める
- 「図書館きんちゃく」を決める
- 「図書館の本のおうち」を決める
図書館バッグ
借りる冊数が少ないなら、数冊の本が入るのにちょうどいい大きさの「図書館バッグ」を決めて、移動と収納を兼ねるのがおすすめです。
こちらのバッグは、メッシュ素材で中身が見えるところがおすすめ。
バッグに入れっぱなしでも借りてきた本が見えるので、「移動と収納を兼ねやすい」といえます。
読んだらバッグに戻す、図書館へ行くときはバッグをそのまま持ち出すだけ。
リビングや子ども部屋など、フックが1つあれば引っ掛けるだけで収納も完了します。
バック自体が軽量なのも嬉しいポイントです!
図書館バッグ用に壁にフックをつけるなら、無印良品の「壁に付けられる家具」シリーズがおすすめ。
壁穴が目立ちにくく、家具見えするデザインなのでインテリアの邪魔をしません。
床材の色に合わせたり、目立たないよう壁の色にあわせてホワイトグレーを選んでもいいですね!
コロンとした見た目も癒やされます!
図書館きんちゃく
借りる冊数が少ない場合は、本が入る大きさの「図書館きんちゃく」を用意するのもおすすめ。
図書館用として役目を終えたあとでも、保育園や学校の体操服入れなどに使い回しできるのがきんちゃくのいいところ。
持ち手がついているタイプだと持ち運びがしやすいうえ、ナップサック型を選べばそのまま背負って図書館に行くことができます。
最近はナップサック型の体操着袋を指定している小学校も多いので、長く使えそうですね!
図書館の本のおうち
もしバックや袋ものにピンとこなかったら、自宅に「図書館の本のおうち」=(絵本の居場所)を作ってあげるのもおすすめです。
もちろん、おうちにある本棚に図書館の絵本専用のスペースを確保しておくのもいいですね。
その場合は、おうちの絵本とわけて管理できるようラベリングすることをおすすめします。
ラベリングの例

文字が読めるお子さんの場合は、「としょかんのほん」などとラベリングしたり、文字が読めない小さなお子さんには本のマークや目印になるシールなどでラベリングすると認識しやすくなります。
無意識のうちにおうちの絵本と混ぜてしまわないよう、「図書館の絵本の居場所はここだよ!」と示してあげることが大切。
ママが毎回教えなくても、ラベリングに従ってお片付けができるようになります。
ラベリング。最初はひと手間かかるけど、あとは安心して見守れるようになる工夫です。
移動できる絵本のおうち
持ち運びできる絵本の居場所がお好みなら、マガジンラックという手もあります。
図書館に行くときは移し替えの手間がかかりますが、少量なら負担も少ないかもしれません。
それより、そのまま置いていてもおしゃれな見た目で気分があがる!インテリアに馴染むのが嬉しいですね。
たかが収納だけど、気分の問題って大切だと思います。ぜひお気に入りを見つけてください!
子どもと作る!絵本収納のコツ
少しわかってきたけど、やっぱり収納は苦手。なにかコツはありますか?
このあと、絵本収納のコツもお伝えしていきます。
子どもが使う収納を決めるときに大切なコツは、子どもと一緒に確認しながらすすめることです。
- 手が届くかな?
- 場所はわかりやすいかな?
- ラベリングは理解できるかな?
これらをひとつひとつ、子どもと一緒に確認しながらすすめましょう。
ちなみに、図書館バッグや図書館きんちゃくを決めるときも、お子さんと一緒に決めます。
例えばバッグやきんちゃくの場合、素材によっては形が崩れやすかったり、出し入れの際に絵本がひっかかって出し入れしづらいものもあります。

形が崩れやすい、絵本が引っかかってしまうなど、出し入れの際に感じるストレス。それはそのままお片付けのストレスになってしまうことも・・・
子どもができるかどうか、わかるかどうか確認しながら収納を決めることは、子どもにぴったりの収納を見つけるための大切なステップなんです。
絵本を読む主役は子ども。絵本収納の主役も子ども。ぜひ、子どもと一緒に自分にぴったりの絵本収納を見つけてくださいね!
ついつい自分だけで決めがちなので、子どもと一緒に決める過程も楽しみたいと思います。
絵本の居場所をつくろう

先ほどお伝えした3つの方法に共通するのは、借りてきた絵本の居場所があるということ。
いずれ返さなければならない図書館の絵本だからこそ、返すときに慌てないよう絵本の居場所をきちんと決めておくことが大切です。
小さな子どもでも手に取りやすい、戻しやすい収納。
子どもでも扱いやすい絵本の居場所がちゃんと決まっていれば、図書館へ行く前に慌てて絵本をかき集めることもありません。
大人が少しの工夫をしてあげるだけで、小さな子どもでもできることは意外と多いもの。
忙しい大人にも小さな子どもにも優しい収納になれば、図書館絵本とのおつきあいもより充実したものになりますね。
絵本収納おすすめグッズまとめ
今回ご紹介した絵本収納におすすめのグッズをおさらいします!
 | たくさん絵本が入る | Amazon | 楽天 | Yahoo |
 | 軽くて中身が見えるバッグ | Amazon | 楽天 | Yahoo |
 | 絵本バッグの定位置はこのフックで | Amazon | 楽天 | Yahoo |
 | 数冊しか借りない場合は袋タイプが◎ | Amazon | 楽天 | Yahoo |
 | 絵本のおうちがあると散らからない | Amazon | 楽天 | Yahoo |
 | 可愛い見た目で子どもが扱いやすい | Amazon | 楽天 | Yahoo |
 | 持ち運びできる | Amazon | 楽天 | Yahoo |
まとめ
今日は、「【無印良品】お片付けのプロ推薦!図書館絵本の頑張らない収納法」として、図書館で借りてきた絵本の頑張らない収納法について解説しました。
わが家のようにひんぱんに図書館に行くママも、そうでもないママも。
今まで本は買っていたので図書館は利用したことがなかったというママも、図書館絵本の「収納と移動を兼ねる方法」で、図書館を使い倒してみてください!
最適な収納方法は、図書館の利用頻度や借りてくる本の冊数、子どもの年齢や生活スタイルによって変わります。
一度決めた収納方法も、子どもの成長や暮らしの変化に合わせて見直しながら、図書館とのお付き合いを楽しんでみてくださいね。
「兼ねる収納」で、みなさんの毎日がより豊かで楽しいものになりますように!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
書類の整理にお悩みのママは、スマホひとつでカンタンに書類整理ができる意外な方法があります!

こどもと楽しむシンプルなくらしをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。