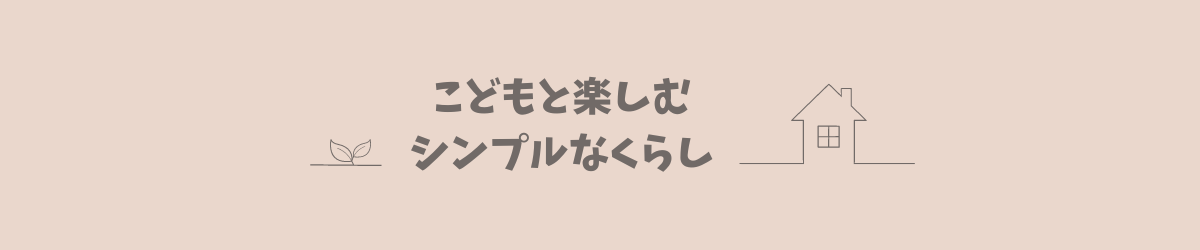もうすぐ保育園に預けるんだけど保育園の洗礼が怖いな・・・
今まさに保育園の洗礼を受けています・・・参った・・・
それは大変ですね。わたしも復帰当初は大変でした。
保育園の洗礼ってどんなもの?
実際に洗礼を受けて困っている!
そんなママのために、3人の子育てと3回の職場復帰の経験をしたわたしだからお伝えできる準備と対策について解説します!
対策だけを読みたいかたは、もくじを開いて「職場復帰前にやっておくべきことは?」まで読み飛ばしてくださいね!
この記事でわかること
- わたしの経験した保育園の洗礼
- 保育園の洗礼に対する準備と対策
この記事を書いている人
4児のママ、あいです!
- 2男2女のママ
- 整理収納アドバイザー1級
- 頑張らずに子育てを楽しむ方法について発信中!
保育園の洗礼はいつまで続いたのか?
慣らし保育でイキナリつまづく

2022年8月初旬。10ヶ月の長男(第3子)の入園が決まりました。
長男(当時10ヶ月)は、慣らし保育中から胃腸炎になってお休みを繰り返し、10日あるはずの慣らし保育がその半分もできず・・・。
大した「慣らし」をできないまま復帰の日を迎えました。
さいわい、先生方や保育園の環境にはすんなり馴染んでくれたけれど、心も身体も落ち着かない慣らし保育期間でした。
復帰直後もドタバタ
復帰から1週間が経ち、時短勤務で仕事をしながら3人の子育てをする毎日にもだんだん慣れてきた頃。
初めての週末は長女の腹痛と長男の風邪のための受診で終わりました。
これからしばらくはこんな週末が続くのかもしれない・・・そんなふうに思いながらの過ごした久しぶりの「週末」でした。
その2日後、二女が発熱とのことで園からお呼び出し。風邪症状の長男は念のためお休みさせていた日の午後でした。
二女は3日間発熱が続き、解熱したと思ったらつぎは長女が発熱。長男は熱こそ出していないもののずっと咳と鼻水・・・
次の週末もやっぱり受診で終わりました。しかも3人まとめて。
保育園の洗礼恐るべし。だけどこれもわたしにとっては3回目。
お熱のドタバタは覚悟していたつもりでしたが、さすがに3人もいると予想を上回るペースかもしれない・・・
翌週にはついに長男が発熱。ずっと風邪症状が続いていただけに、よくここまで頑張ったねという心境でした。
ここ10日間のあいだは子どものうち誰かしらが熱を出しているわが家。
夫と交代で休みをとって看病しました。
10ヶ月の長男はまだ母乳を飲んでいたので、わたしが看病に当たることが多くまともに仕事に行けません。
復帰したものの、朝からお休みの連絡を入れては謝ってばかりでした。
ちなみに4日間続いた長男の発熱の原因は、突発でした。
保育園の洗礼には大人も注意

4日間続いた長男の熱が下がった翌日。なんとわたしが発熱しました。
40度の高熱が3日間続くなか、意識朦朧としながら必死の思いで授乳もしました。夜間も這い出て授乳・・・つらい!!
熱が出たのが週末だったので、翌月曜日に受診するとなんと「肺炎」でした。
そのままその週は仕事を休んで自宅療養。
喘息持ちのわたしにとって、子どもたちがもってくる風邪菌やウイルスは本当に怖いです。
長男は、わたしが自宅療養中の週後半にもまた熱を出しました。
わが子の通う保育園は解熱から24時間経過しなければ登園できないルール。
たとえ一晩で熱が下がったとしても、翌日は登園出来ないのです。
わたしが自宅療養中だったので、自分の療養と看病を同時並行できたけれど、なんだか明日が見えない綱渡りのような毎日。
そうやって順番に、一人、またひとりと倒れ・・・ようやく復帰して1ヶ月。
この間まともにできた仕事はありませんでした。そして、まさか自分が肺炎になって倒れるなんて思いもしなかった!
さいわい、夫はずっと無事だったけれど、その2週間後には二女がまた発熱。
二女はあまり熱を出さない子で、0〜1歳児クラスの頃のお呼び出しは数えるほどだったので、ここ最近の生活ぶりは身体に応えたのかなと感じました。
復帰3ヶ月目でやっと落ち着く

結局、保育園の洗礼はいつまで続いたのか・・・
わが家の場合、8月に復帰して、翌々月の10月は誰も体調を崩さずに駆け抜けられました。
家族みんなが元気で、朝起きたら普通に保育園に送っていって仕事に行けて。
午後になってもお呼び出しの電話が鳴ることなく、普通に仕事を終えて普通にお迎えに行ける毎日がこんなに幸せだなんて。
噛みしめるように過ごしたし、仕事も頑張れました。
復帰直後は子どもたちが次々倒れ、子どものたちの心配をしながら仕事の心配もしなければならないストレスフルな毎日。
明日も出勤できるかわからない中、家族のためにも自分のためにも、時短勤務とノー残業を貫いてきました。
11月は長男と二女がそれぞれ1回ずつお熱でお呼び出しがあったけど、復帰して初めての小旅行にも行けて、日頃の頑張りを労うことができた1ヶ月でした。
そんなわけで、ドタバタと3回目の職場復帰を果たしたのでした。
そんなドタバタの経験をしたわたしだからわかる、保育園の洗礼を乗り切るための準備と対策とは?!次から詳しく解説します!
1人目のときは落ち着くまでに半年かかったので、今回は早いほう。インフルなどが流行る時期だとさらなる洗礼が待っているかも・・・準備と対策は万全にしておきたいですね。
保育園の洗礼!準備と対策
ここからは、保育園の洗礼を乗り切る準備と対策について解説します。
怯えていても仕方がない!来るものは来ます(笑)
だからこそ、しっかりと対策して。慌てることなく保育園の洗礼と戦いましょう!
お呼び出し時の対応を決めておく

保育園の洗礼の試合開始のゴング。それはたいてい「お呼び出しの電話」。
あるとき急にかかってきます。
急にお呼び出しの電話がかかってきたけどどうすればいいの?!目の前の仕事は?!
そう思うかもしれませんが、お呼び出しの電話がかかってきたらどんな状況であっても誰かしらがお迎えにいかなければなりません。
それが出社直後であったとしても。
いつも急にかかってくるお呼び出し電話に備えて、お迎えの手順を決めておくことをおすすめします。
発熱などで保育園からお呼び出しの連絡があった場合、だれがどのくらいの時間でどのようにお迎えに行くのか、予めシュミレーションしておくことが大切です。
夫婦のどちらかなのか、あるいは祖父母やその他の親戚なのか・・・誰が対応できるのかが最も大切なポイントです。
わたしの場合をお話します。
- 園からのお呼び出しの連絡がある(第一連絡先は母であるわたし)
- 同じ会社に勤める夫に連絡する
- どちらがお迎えに行くのか、お迎え後の受診はどうするか、他のきょうだいのお迎えはどうするか、翌日の看病はどうするかを相談
- お互いに仕事を調整し、片方がお呼び出し対応のため退勤
うちの子の園では、だれか一人でも発熱するときょうだい全員帰宅しなければなりません。
3人目ともなれば、こういった緊急時にもスムーズに対応できるほど慣れてきましたが、1人目や2人目のときと違うのが「きょうだい対応」。
一人目のときはお呼び出しのたびに夫とケンカをしていたような気がしますが、今では協力して子育てする夫と同じ方向を向いて対応できるようになったことを心強く感じています。
ちなみに緊急連絡先の第1位の人は「お呼び出しがあるかも」というプレッシャーを感じながら仕事をすることになります。
電話を受ける人とお迎えに行く人を夫婦などで分担しておくと、精神的な負担を分散することができます。
できるだけママだけ、パパだけに負担が偏らないよう分担することをおすすめします!
- お呼び出しには誰がどのように対応するのかシュミレーションしておく
- 「緊急連絡先第1位の人」と「お迎え担当の人」を分担しておく
受診先を決めておく

急な発熱などでお呼び出しになった場合、必ずと言っていいほどしなければならないことが「受診」です。
この急な受診に備えて、かかりつけの病院以外の受診先を見つけておくことが大切です。
小児科は水曜日や木曜日が休診日のことが多いですが、子どもは疲れがたまってくる週後半に体調を崩すことが多いんです。
わたし自身、いざ受診しようと思ったらかかりつけが休診日!そんなことがよくありました。
また、かかりつけが受付終了した平日夜間に受診したい場合や、休日はどうするのか。
受診が必要となる曜日、時間帯、症状に応じて、受診しやすい病院はどこなのか目星をつけておくと慌てません。
その際、受診時の予約は取りやすいか、当日予約や当日順番取りはできるのか、先生の専門分野はなにかなどもチェックしておくようにしてください。
さらに病院の連絡先はあらかじめスマホの電話帳に登録しておきましょう。病院へのアクセス、駐車場の有無、薬局の場所まで確認しておくとバッチリです。
その他にも院内での待ち時間が少なくて済むか、処方薬をスムーズに受け取れる薬局かなどもチェックしておくとよいでしょう。
(LINEで処方箋の写真を送って、待ち時間を短縮できる薬局もあります)
- かかりつけが受付していない時間帯の受診先を決める
- 予約を取る方法(当日予約や順番取りができるかなど)を確認する
- 先生の専門分野はなにか確認する
- 病院の電話番号を登録する
- 病院へのアクセス方法を確認する
- 病院の駐車場の有無を確認する
- 薬局の場所や処方箋の提出方法を確認する
- 院内の状況(キッズスペースの有無など)を確認する
具合の悪い子どもの対応をしながら受診先を探すのは大変です。
余裕のある平常時にこれらの下調べをしておくと緊急時でも落ち着いて対応できます。
また、受診時には発熱時の園での様子、食欲、熱の経過なども保育園から聞き取っておくことが大切です。
保険証やこども医療費受給者証、診察券、母子手帳等はわかりやすく一箇所にまとめておいてくださいね。
- かかりつけ以外の受診先を見つけておく
- 受診先の詳細情報(予約方法やアクセスなど)も確認しておく
- 園での様子を医師に伝えられるようにしておく
- 保険証などの貴重品をわかりやすい場所にまとめておく
園のルールを確認しておく

子どもの体調に異変があった場合どのように対応するのか。
解熱後24時間は登園できない、発熱の原因がわかるまできょうだいも登園できない、感染症の種類や症状によっては○日間登園停止となるなど。
園によって、発熱や感染症にかかった際の対応についてさまざまなルールが定められています。
それらをすべて暗記する必要はありませんが、すぐに確認できるよう母子手帳や診察券などと一緒に保管しておいたり冷蔵庫に貼り出しておくと便利です。
受診時には医師に病名を確認し、園のルールと照らし合わせた上で、治癒証明証の作成の相談や再受診の日程を相談するとよいでしょう。
園のルールによっては呼び出し当日から数日間は仕事と看病の調整が必要な場合があります。
呼び出し当日から翌日以降、登園できるようになるまでの看病は誰が行うのか、症状が長引いた場合はどうするのか。
子どもが小さいほど、子どもの数が多いほど呼び出し回数のリスクが増すので、慎重に備えるようにしてくださいね。
- 園の感染症に関する対応のルールを確認しておく
- 受診の際は園のルールを踏まえて医師と今後の対応を相談する
- 登園できない期間が長引く可能性も考慮して対応を検討する
いつ休んでもOKな仕事スタイルにする

子どもの体調不良は予測できません。
朝は元気だった子どもが急に熱をだし、仕事中に突然「すぐにお迎えに来てください」と電話がかかってくるのです。
だから、できるだけ急に休んだり早退することになっても大丈夫なように対策をしておくと安心です。
例えばわたしの場合、いつでも引き継ぎができるようパソコン内のデータや書類、デスク周りを整理整頓しておいたり、担当内で随時進捗を共有するなどしています。
それから、期限のある仕事はギリギリではなく早め早めに終らせることも心がけています。
働くママにとって、朝から夕方まで何事もなく仕事ができるって本当に幸せなことです。
そして、急に休んだり早退することになっても理解し協力してくれる職場や上司、同僚には感謝の気持ちでいっぱいです。
子どもが小さい時期は仕事への貢献度が下がるかもしれませんが、いつか自分が逆の立場になったときにはお返しができるよう、今は力を蓄えるとき。
「おたがいさま、おかげさま」の精神で、周囲への気配りも忘れずにいたいと思っています。
- 急なお呼び出しに備えて、いつでも休めるように仕事を調整しておく
- デスク周りの整理整頓や進捗の共有は日頃から行っておく
- 期限のある仕事は早めに終わらせる
- 職場への感謝の気持を忘れない
わたしも1人目のときからうまくこなせたわけではありません。3人目でやっとです!少しずつ、ママ・パパも成長していきましょうね。
看病グッズを買っておく

保育園児は園内で常に風邪菌やウイルスにさらされています。
子どもの急な体調不良に備えて、看病に必要なグッズも用意しておきましょう。
発熱対策
保育園からのお呼び出し理由ナンバーワンはなんといっても発熱!
そうなると、高機能な体温計があるととっても便利です。
発熱すると、一日に何度も体温チェックする必要があるので、測定結果がすぐ確認できる体温計がおすすめ。
こちらは1秒で計れる体温計。非接触型なら子どもの負担にもなりません。
発熱時によく使われるアイス枕には、冷凍してもカチコチに凍らないタイプがあります。
カチコチに凍ると子どもが嫌がりそうだもんね。
繰り返し使えるので、夏場の寝苦しい夜などにも活用できますね。
そして、発熱時に便利な冷却シートには子ども用があります。
小さな赤ちゃんには赤ちゃん専用のものを。
子ども用の熱さまシートは、大人用のシートを小さくしただけでなく、メントールの量も調整してあるそう。
大人用シートのメントール量では小さな子どもには量が多く刺激が強いので、子ども用を用意しておくべきですね。
熱の不快感が軽減すると体調の回復も早まりそうです。
ただ、発熱したからと言ってすぐに身体を冷やすのはNG。
悪寒があるときは身体を温める必要があるので、いきなり冷やさずに子どもの様子をよく観察してください。
鼻水対策
子どもの体調不良は発熱だけでなく咳や鼻水、嘔吐や下痢なども起きてきます。
体温計、マスク、手袋、ビニール袋、アルコール消毒液、鼻水吸引器のほか、食欲不振に備えてOS1(オーエスワン)などの経口補水液、お薬が飲みやすくなるゼリーなども常備しておくと安心です。
早く風邪を治してあげるためにも、自分を鼻水をかめるようになるまでは鼻水吸引器が有効です。
強力な吸引力を重視するなら卓上タイプがおすすめ。
寝室やリビングなど、気軽に持ち運んで使用するならハンディタイプがおすすめです。
わたしは卓上タイプで鼻水吸引しまくりました。鼻がすっきりするとぐっすり眠れるので、風邪が早く良くなる好循環に入れます!
電源不要な手動タイプの吸引器もあります。
こちらは電動タイプに比べると吸引力は劣りますが、ちょっとした鼻水をぱぱっと吸い取りたいときに重宝しました。
飲み薬対策
体調不良で受診すると、お薬を処方されることが多いです。
でも、小さなお子さんだと処方されたお薬を嫌がって飲まなかったり、上手に飲めないこともありますよね。
早く回復するためにもしっかり飲んで治してほしいです。
そんな場合に備えて、病院で処方されたお薬が飲みやすくなるグッズを用意しておきましょう!
おやつ感覚でおくすりを服用できるので、はやく症状を和らげてあげられますね。
お薬は粉薬で出ることも多いので、常備しておくと安心です。
嘔吐・下痢対策
保育園の洗礼対策として、嘔吐や下痢の対策も欠かせません。
ノロウイルスなどに感染した子どもの汚物処理には次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。
ふつうのアルコール消毒ではウイルスが死滅しないと聞いて驚きました!(全く無意味な消毒をしていました・・・)
ノロウイルスなどは飛沫感染します。
汚物を処理するときは無防備な格好で対応せずに、手袋にマスク、できれば防護服を着て、消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使いましょう。(大人がもらうと大変なことになります・・・!!)
わが家では次亜塩素酸ナトリウムを常備しています。
子どもの体調不良は急にやってくるもの。気づいたらすぐに備えましょう。
手袋や帽子などがセットになった汚物処理キットもあります。
何を用意したらいいのかわからないなら、キットを備えておくのもアリですね。
- 鼻水吸引器は保育園児ママの必須アイテム
- 風邪を早く治すなら鼻水はこまめに取る必要あり
- 飲みづらいお薬に備えてゼリーがあると便利
- 汚物の処理に備えて次亜塩素酸ナトリウムを用意しておく
保育園の洗礼に巻き込まれない
この記事を読んでいるママは、すでに保育園の洗礼に巻き込まれて困っているママが多いと思いますが、そもそも保育園の洗礼に巻き込まれない対策も強化したいところ!
こちらは食品にかかっても安心のアルコールスプレー。
子どもが手を洗いたくないとぐずったときなど、シュシュッと消毒しています。
また、風邪予防の基本である「手洗いうがい」も、小さな子どもが取り組みやすくなる一工夫を!
こちらのオートソープディスペンサーはサラヤ社製。シンプルな見た目と安定感のある使い心地がお気に入りで、もう5年以上愛用しています。
電池がいらない充電式なのもおすすめしたいポイントの一つです。
バッテリーはいつ充電したか忘れるほどの持ちの良さ!センサーの反応が良く小さな子どもでも使いやすいです。
大人のための洗礼対策も必須
子どもが保育園の洗礼を受けて体調を崩すと、必ずと言っていいほど大人にも感染します。
子どもからうつされた風邪は手強い!
根拠はないですが、保育園の洗礼を3回経験してそう感じています。
だから、子どものための対策と一緒に大人のための対策も。
基本的には子どもの看病グッズと同じで大丈夫ですが、必要に応じて風邪薬などを用意しておきましょう!
お仕事はそう簡単に休めないですもんね。
感染症に負けない身体をつくる

保育園の洗礼は避けられなくとも、なるべく苦しい思いをせずに過ごしたいですよね。
それには、風邪に負けないつよい身体づくりも大切です。
風邪にかかっても重症化しないとか、そもそも風邪にかからないといったつよい身体づくり。
わたしが3年間続けている「重ね煮」という調理法なら、つよい身体をつくるごはんがほったらかしで作れるんです!
こちらの本を参考にしています。
3番目の長男は離乳食期から「重ね煮」を食べているせいか、長女や二女に比べると風邪や発熱に強い!
男の子は女の子に比べて身体が弱いと聞くので心配していましたが、ほとんど体調を崩すことなく順調に登園できています。
なんと言っても「身体は食べたものでできている」。まいにち口にする食べ物がいかに大切か、考えずにはいられません。
大人が感染しないためにも家族でつよい身体づくりに取り組んでもらいたいです。
家族で重ね煮を食べれば大人にもメリットがあるのね。
お呼び出しばかりだった1人目の時は「重ね煮」を知りませんでした。重ね煮を初めて4年以上。今は子どもたちが体調を崩しづらくなり、「重ね煮」の効果を感じずにはいられません。
「重ね煮」についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

復帰後の食事作りをラクに
保育園の洗礼も大変ですが、ワーママにとって復帰後の食事作りも大変ですよね。
「重ね煮」はつよい身体づくりはもちろん、調理過程がカンタンでしかもおいしくできることが魅力の調理法。
一度身につけてしまえばどんどん応用できるカンタンさなので、復帰後の食事作りにもぜひ活用してほしいです。
重ねて煮るだけなのでカンタンなんです!!
そして、復帰後の食事作りで特にネックなのが、離乳食づくりとの両立です。
1歳前に復帰したのでまだ離乳食を作らないといけなくて・・・
子ども3人、生後10ヶ月で復帰したわかります。そんなわたしの離乳食づくりの工夫をこちらの記事で紹介しています!

- 保育園の洗礼に怯えるばかりでなく、病気に負けないつよい身体をつくる
- 強い身体づくりには毎日の食事が大切。「重ね煮」なら簡単に作れる!
保育園の洗礼対策まとめ
今日は3人の子育てと3回の職場復帰の経験をしたわたしだからお伝えできる、保育園の洗礼を乗り切る準備と対策について解説しました。
備えておくことが大切だとわかりました!
3回の職場復帰を経験して学んだ「保育園の洗礼対策」。洗礼に巻き込まれる前に準備しておくべきことのポイントをおさらいします。
- お呼び出し時の対応を決めておく
- 受診先を決めておく(かかりつけ以外も)
- 園の感染症ルールを確認しておく
- いつ休んでもOKな仕事スタイルにする
- 看病グッズを買っておく
- 感染症に負けない強い身体をつくる
子どもの体調不良は予測できません。だからこそ対策や準備は入念に。
少しでも安心して職場復帰ができるように応援しています!
わたしは保育園に預けること自体が寂しくてたまらないです。
保育園に預けることが寂しいママは、こちらを読んでみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
こどもと楽しむシンプルなくらしをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。